「予想以上に大規模な『貧酸素水塊』を確認 諫早湾は酸欠状態」
2001年8月に実施した有明海の自然環境調査の結果を緊急発表
2001年8月17日
有明海奥部における底層の溶存酸素濃度(速報)
(財)日本自然保護協会
1. はじめに
本報告は、2001年8月5日~7日に当協会が実施した「有明海の水質・潮流調査」の中の溶存酸素濃度の結果を速報としてまとめたものである。
近年有明海および諫早湾内で報告されている底生生物の減少は、有明海の水質悪化と諫早湾内の潮汐運動の低下による水温成層の安定によって生じた貧酸素水塊が原因であると推測されている。貧酸素水塊の発生は「潮受堤防の建設と干潟の埋立→潮汐運動の低下と水質の悪化→水温成層の発達に伴う底層の貧酸素化→底生生物の死滅→水質・底質の更なる悪化→底層の更なる貧酸素化」と、有明海の生物生息環境の悪化に拍車をかけている可能性がある。また、貧酸素水塊の発生は夏期の赤潮発生の一因となっているとの研究例もあり、近年の有明海における赤潮発生件数の増加との関連も示唆される。
有明海における貧酸素水塊の発生については、これまでに佐藤ら(2001年、岩波「科学」7月号)によって1997年6月、1999年6月に観測されてい
る。それによれば、貧酸素水塊は諫早湾湾口部を中心に広がっていることから、諫早湾湾口部にある採砂跡の溝(諫早湾干拓事業用の砂採取のため約150haの範囲内に幅15m、深さ4mの溝が多数掘られている)で貧酸素水塊が形成されていると推測している。
一方、第三者委員会が3月に発表したまとめでは、「夏期の貧酸素水塊の発生の実態については現時点では十分には把握されていない」としているが、農林水産省の実施したモニタリング調査では表層と中層の溶存酸素濃度しか調査していないため、底層における貧酸素水塊の発生の実態は明確に把握できなかった。
当協会が2001年8月5~7日に行った調査では、1)調整池から排出された栄養塩を多く含む淡水の諫早湾内および有明海全域への拡散状況、2)植物プランクトン発生状況、3)貧酸素水塊の発生状況の把握に重点を置いた。水質や植物プランクトンについては現在分析中であるが、貧酸素水塊の発生については緊急に情報を公開し、行政側に緊急調査を要求する必要があると考え、今回調査速報として報告する。
2. 調査方法
有明海全域の水質調査地点を図1に示した。諫早湾内およびその周辺の25地点(a~c、1~22)は8月5日、有明海中央部(23~30)および有明海奥部(31~36、筑後川河口)は8月6日、島原沖(37、38)は8月7日に行った。
溶存酸素濃度の測定は、多項目水質計(HORIBAU-21)により主要な地点では鉛直変化を、その他の地点では表層(0m)および底層のみ測定を行った。底層の測定では、底泥の巻き上がりの影響を防ぐため海底から0.5~1mの水深で測定を行った。そのため、底泥直上の溶存酸素濃度は本調査で得られた値よりも低くなることが考えられる。また8月7日には、St.5(図1)と小長井沖(32°55’035N 130°11’996E)において、溶存酸素濃度の鉛直変化の測定も行った。
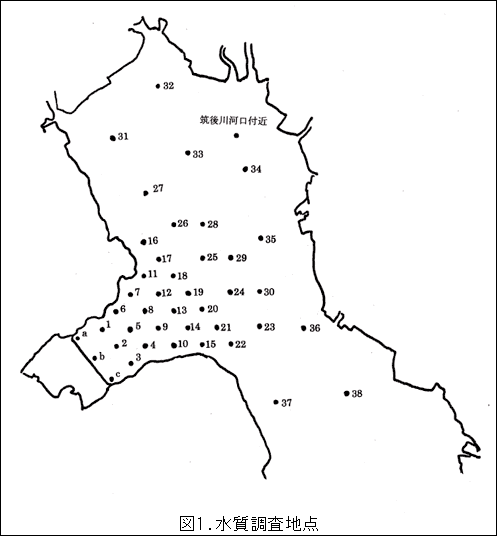
3. 結果
2001年8月7日にSt.5と小長井沖において測定した溶存酸素濃度の鉛直変化を図2に示した。溶存酸素濃度は表層では6 mg L-1以上とほぼ飽和濃度(6.34mg L-1)と同程度になっているが、中~底層で急激に減少し、海底から1mの水深では2mg L-1以下となっている。この結果を説明すると以下の通りである。表層は空気中から酸素が十分に供給されるが、表層水は太陽に温められ、温度による水の密度変化から水温成層と呼ばれる密度成層が形成される。この様な状態になると表層と底層の水は混ざりにくくなり、表層水に十分に含まれている酸素が底層まで到達しにくくなる。また、密度成層による鉛直混合の減少は塩分の差によっても生じ、長期化するとSt.5で測定されたような底層水の溶存酸素濃度の減少、貧酸素水塊が形成される。小長井沖でもSt.5と同様に、表層から底層にかけて溶存酸素濃度が急激に低下し、6m以深では1 mg L-1以下となっている。
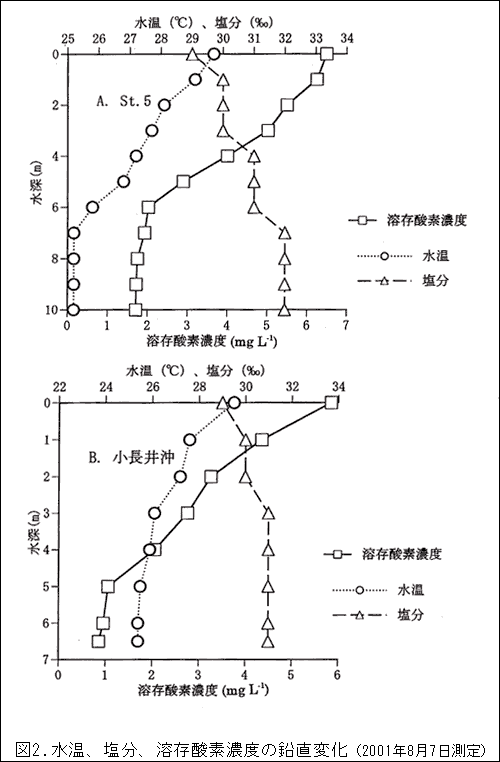
有明海奥部における表層(0m)の溶存酸素濃度の分布を図3に、底層の溶存酸素濃度の分布を図4に示した。表層の溶存酸素濃度は、有明海湾奥に行くに従い減少してゆく傾向が見られた。特に筑後川河口付近では4mg L-1以下と低い値が測定されたが、この地点での測定は干潮時に行ったため、干潟が発達したこの地点では底泥の巻き上がりによる酸素の消費が表層まで大きく影響していたと考えられる。また、諫早湾内では、殆どの調査地点で6 mg L-1以上とほぼ飽和濃度に近い高い値を示していた。
底層の溶存酸素濃度測定の結果、大規模な貧酸素水塊が形成されていることが明らかとなった(図3)。諫早湾奥部では、最も低い地点で0.53mg L-1(飽和度8.4%)という溶存酸素濃度であり、1mg L-1以下(飽和濃度の8.4~13.1%)の値も広範囲で観測された。また、3mg L-1以下(飽和濃度の50%以下)の溶存酸素濃度は、諫早湾湾口部および佐賀県太良沖の広い範囲で見られた。
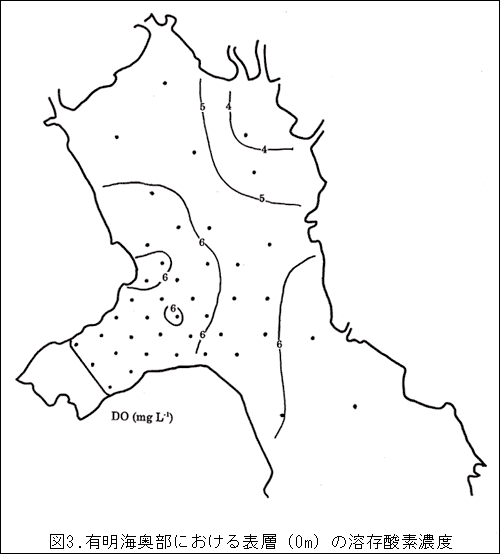
4. 考察
(貧酸素水塊の発生)
本調査の結果、これまでに佐藤ら(2001)の1997年6月、1999年6月の観測と同様に、今年も諫早湾内を中心に大規模な貧酸素水塊が形成されていることが明らかとなった。
諫早湾干拓地域環境調査委員会が毎年まとめている「環境モニタリング結果」によると、「潮受堤防外のDO(溶存酸素濃度)年平均値および最大値はほぼ横ばいで推移している」と述べているだけで、貧酸素水塊についてはこれまでその発生事実を認めていない。この理由として、環境モニタリングでの海域水質は諫早湾中央と湾口付近の合計4地点でしか行われていないこと、しかも溶存酸素を測定した水深が表層と中層(水深の1/2の水深)の2点だけであり、底層のデータは取られていないことが挙げられる。本調査結果(図2)を見れば明らかなように、海水中の溶存酸素濃度は海底から数メートルの水深で急激に減少する。
よって、環境モニタリングで行っているような中層までの溶存酸素濃度の調査では検出されないのは当然のことと言える。
(底生生物への影響)
諫早湾内のアサリ養殖場では、毎年夏期にアサリの大量死が発生することが報告されている。一般的に二枚貝は貧酸素条件に強い生物であり、ある一定期間であれば無酸素条件下でも生存が可能なことが知られている。中村幹雄(1997年、博士論文「宍道湖におけるヤマトシジミと環境との相互関係に関する生理・生態学的研究」)は、無酸素条件下では2日で約半数、4日で全個体が死滅することを報告している。また、溶存酸素濃度が低下すると生物に対して毒性の強い硫化水素の発生が生ずるが、これも底生生物の生残に大きな影響を与えることが知られている。風呂田(1991年、沿岸環境研究ノート、28号)によると、東京湾奥部では溶存酸素濃度が2mg L-1以下になると底生生物の出現種数が急激に減少する傾向が見られている。本研究で認められた溶存酸素濃度1mg L-1以下の貧酸素水塊がどの程度続けばアサリをはじめとする底生生物に致死的な影響を与えるかについては今後慎重な検討が必要であるが、成長を制限するには十分に低い酸素濃度となっている可能性がある。
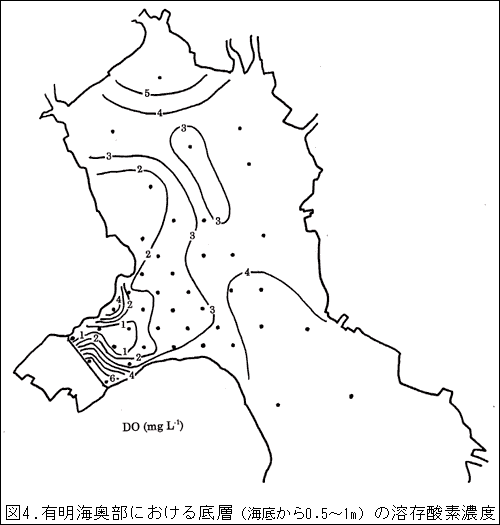
(貧酸素水塊の移動)
諫早湾北部と南部で底層の溶存酸素濃度が4mg L-1以上と比較的高い値が観測されているが(図4)、貧酸素水塊は潮の満ち引きや風の影響により広範囲に移動することが考えられるため、今回の調査で底層の溶存酸素濃度が比較的高かった地域でも、諫早湾奥で観測された溶存酸素濃度1mg L-1以下の貧酸素水塊の影響を受ける可能性があることを注意する必要がある。
また、佐賀県太良沖では溶存酸素濃度2mg L-1以下の水塊が観測されたが、この付近では本調査と同時期に大規模な海底耕耘を行っていたため、底泥を舞上げたことによりバクテリアによる酸素消費が活発化したことによるのか、それとも諫早湾内で発達した貧酸素水塊の影響なのかは確定できない。もし海底耕耘の影響であるならば、嫌気化した底泥に酸素を供給し底質を改善する効果と共に、貧酸素水塊の発生要因となる負の影響も十分に理解した上で実施することが望まれる。
(行政への要求)
本調査の結果、諫早湾内を中心に佐賀県太良沖まで続く大規模な貧酸素水塊が形成されていることが明らかとなった。現在、環境省、農水省農村振興局、水産総合研究センターなどが有明海全域で調査を行っているが、貧酸素水塊の発生は機構は緊急に解明する必要がある項目であることから、今後、成層構造や流況、溶存酸素濃度の連続観測等の手法を用い十分に解析を行うべきであると考える。


